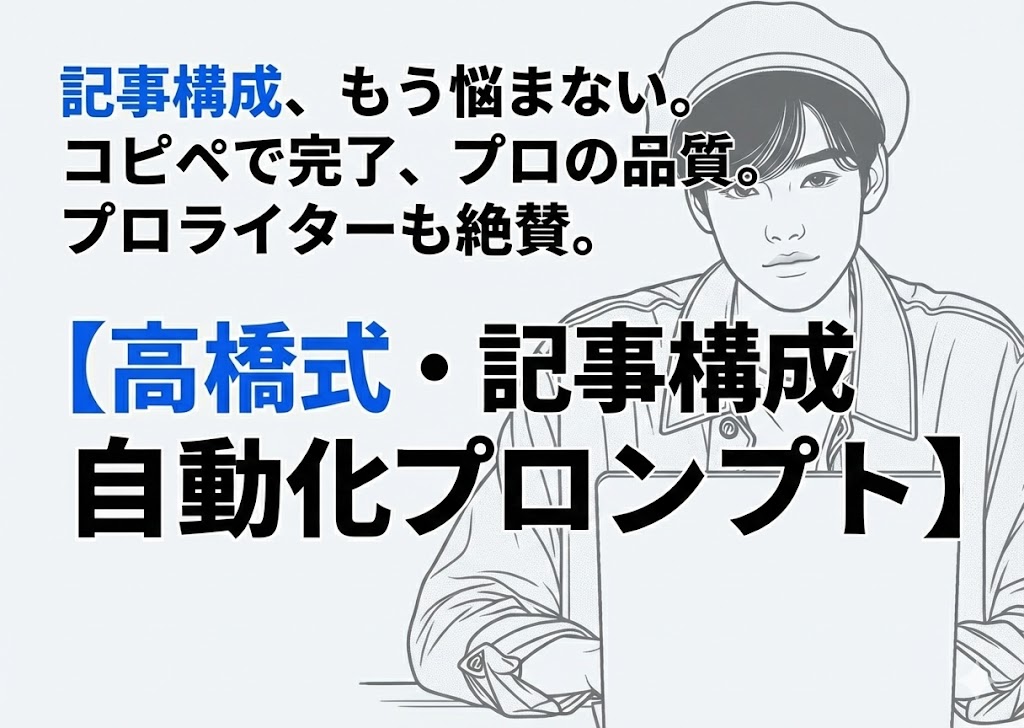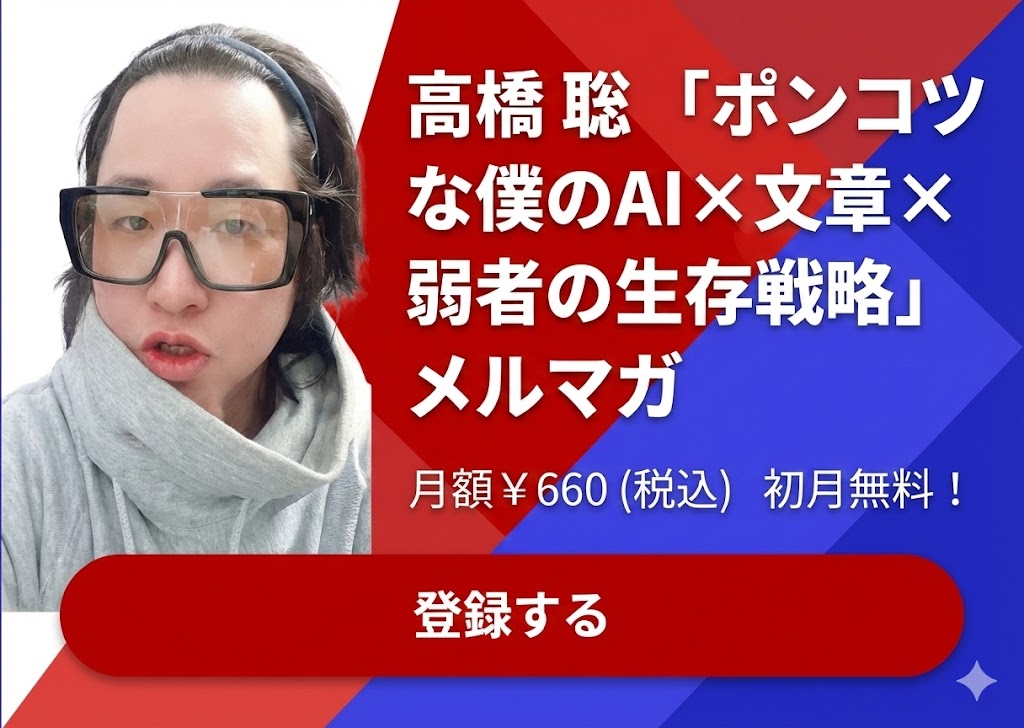頑張って執筆してもなかなか上位表示できない原因の多くは、記事構成の時点でクオリティが低いからです。現役のプロSEOライターが活用しているテクニックを使えば、誰でも検索上位を狙える質の高い記事構成が作れます。
今回の記事では、プロのSEOライターが実践する記事構成の具体的な作り方を8つのステップで徹底的にまとめました。さらに、記事構成の作成を効率化するAIプロンプトや、すぐに使える見出しのテンプレートについても紹介します。
本記事を読めば、SEOで評価される記事構成を作成できる具体的な手順がわかり、執筆効率も飛躍的に向上します。プロSEOライターの思考プロセスとテクニックを学び、ライバルと差をつける高クオリティな記事構成を作成しましょう。
記事構成とは
記事構成とは、SEO記事を作成する工程における設計図や骨組みで、上位表示できるかどうかに大きく影響する要素です。
家を建てるときに設計図が不可欠であるように、わかりやすい記事の作成には事前の構成作りが重要です。記事構成作りは執筆者にとっても書くべき内容が整理され、話の脱線や情報の抜け落ちを防ぐ効果が期待できます。
SEO記事の設計図である記事構成は、検索エンジンに評価されて上位表示されるのが最終的な目標です。そのため、メインキーワードの選定や関連・再検索キーワードの調査を土台にして、記事構成を組み立てていきます。
SEOにおける関連・再検索キーワードとは、検索エンジンで実際にユーザーが行った行動にほかなりません。関連・再検索キーワードを深く調査すれば、検索ニーズやユーザーの課題が浮き彫りとなり、上位表示できる可能性が高まります。
また、SEO戦略としては「上位表示記事より少し優れたクオリティを目指す」がもっとも効率的です。「キーワード調査で読者の課題を明確にする」「上位表示記事より少しだけうえを目指す」を意識して、記事構成を作りましょう。
なぜブログ・アフィリエイト・SEO記事に記事構成が必要か
なぜブログ・アフィリエイト・SEO記事に記事構成が必要かは、以下のとおりです。
- 読みやすさがあがる
- SEOの評価につながる
- 記事制作が効率化する
読者の読みやすさを高め、SEO評価と制作効率の向上に不可欠な記事構成の必要性について押さえましょう。
読みやすさがあがる
緻密な記事構成は、読者が内容をスムーズに理解する手助けとなり、読みやすさを飛躍的に向上させます。あらかじめ記事の骨格を設計すれば、話の展開に一貫性が生まれて論理的でわかりやすい文章になるからです。
また、数百文字ごとにセクションが見出しで区切られて道路標識のように機能し、読者の理解を助けます。くわえて、目次や見出しを見るだけで、記事全体のテーマと各セクションの内容を瞬時に把握できるのもメリットです。
SEOの評価につながる
キーワード調査を行い検索ニーズを捉えた記事構成は、高いSEO効果をもたらし、上位表示の可能性を高めます。
現在のGoogleは、ユーザーの検索意図をどれだけ深く満たしているかを評価基準の核においています。構成作成の段階で検索キーワードの背後にあるニーズを分析し、網羅的な回答を用意すればコンテンツの価値は格段にあがるのです。
1つの記事で満足できる質の高いコンテンツは、検索エンジンに「有益なページ」として認識されます。構成に基づいた見出しタグの適切な階層化は、検索エンジンが記事構造を正確に把握する手助けにもなります。
記事制作が効率化する
執筆前に記事構成を固めるプロセスは、制作全体のワークフローを最適化し、生産性を劇的に向上させます。記事構成は建築における設計図であり、各セクションで書くべき内容や順序が明確になるためです。
全体的な設計図なしに記事を書き始めると、ゴールを定められず迷走し、何度も執筆中に手が止まります。しかし、記事構成がありリサーチを十分に行えば、設計図と材料をそろえた状態のため執筆はスムーズに進みます。
さらに、内容の重複や論理の破綻といった、あとから大幅な修正作業が必要になる危険性を最小化できるのも利点です。結果として総作業時間の大幅な短縮につながるため、まずは構成を練り上げる習慣をつけましょう。
記事構成の作成の前に必要なツールを準備
記事構成に必要となるツールについて、以下の表にまとめました。テキストエディタ以外はすべてクラウドツールですので、登録・アカウント作成をしておきましょう。
| ツール名 | 特徴 |
| ラッコツールズ | ユーザー登録なしで直感的に使えるWebツールを提供するサクサク動作し、多様なジャンルの便利ツールがそろう月間150万PVを達成する人気ツール |
| Ubersuggest | 無料版でも実用的なSEOツールとしてキーワード調査や競合分析が可能日本語対応でサポートも充実するサイトのオーガニックトラフィックやバックリンク数を分析できる |
| GetKeywords | 無料のSEOキーワード分析ツールで検索ボリュームやCPCをチェックするサジェストワードや競合性、SEO難易度も分析可能初心者でも直感的に操作できるインターフェースが特徴 |
| ChatGPT・Gemini・Claude・Grok | 生成AIとしてChatGPTは汎用的な会話、GeminiはGoogle統合、Claudeは安全性重視の特徴がある無料版から有料プランまで利用制限を拡大可能得意分野の違いを活かした活用をおすすめする |
| Googleドキュメント | クラウド型の文書作成ツールで共同編集と自動保存が可能基本無料で複数人での推敲がどこからでも行える変更履歴の管理も効率的 |
| Notepad++(ほか正規表現対応エディタでもOK) | 無料でWindows向けのシンプルなテキストエディタ正規表現による検索・置換機能が強力で、軽快に動作する大きなファイルもスムーズに編集可能 |
記事構成のための生成AIとして僕が使用しているのは、GeminiとGrok4Fastで、どちらも無料で使えます。
時給5,000円超え!プロのSEOライターが作成した記事構成の実例を公開
「こちらのGoogleドキュメント」は、僕が実際に本記事を執筆するにあたって作成した記事構成です。いまから解説する記事構成の作り方を理解するにあたり、まずは全体的なイメージを持っておくために参照してください。
この記事構成のテンプレート自体は、自由に使っていただいて構いませんので、コピーして余計な部分を消して活用しましょう。
SEOライターに必須!記事構成の作り方・書き方完全マニュアル
SEOライターに必須の記事構成の作り方・書き方完全マニュアルは、以下のとおりです。
- 関連・再検索キーワードを調査
- 検索上位記事のH2見出しの構造を分析・整理
- H2見出しごとに検索してH3見出しを肉付け
- 見出しで関連・再検索キーワードを回収
- 回収できなかった関連・再検索キーワードの見出しを追加
- 内容が重複した見出しがないか確認
- 記事タイトルを決定
- 想定文字数を算出
8つの手順に沿ってキーワード調査から始め、読者のニーズを満たす高品質な記事構成を作成しましょう。
1.関連・再検索キーワードと検索ニーズを調査
記事構成を作成する最初のステップは、関連・再検索キーワードを網羅的に調査し、保存していく作業です。関連・再検索キーワードは読者が抱える表面的な疑問だけでなく、奥にある本質的な悩みまでを映し出す鏡だからです。
関連・再検索キーワードの調査を面倒だと思うライター・ブロガーは多いですが、やらないならSEOはあきらめてください。キーワード調査をしないのは、市場調査せずに新商品をリリースするくらい無謀かつ無駄だからです。
関連キーワードはUbersuggestで調査し、検索ボリュームが10以上なら記事構成に盛り込むため原稿に保存します。なお、1つずつ手作業でコピペするのは気の遠くなる作業なので、GeminiのGem「UbersuggestCSVキーワード・検索ボリューム抽出」を使ってください。
関連キーワードを抽出する作業工程は、以下のとおりです。
Ubersuggest右サイドバー「キーワード概要」から関連キーワードを抽出します。

「キーワード候補」セクションにスクロールし、「すべてを見る」をクリックして関連キーワードを表示します。

「オートコンプリート」「関連」などそれぞれでチェックを入れてから、「出力」→「選択した項目をCSVでエクスポート」をクリックしてください。
すべてのタブを一度に出力はできないので、タブごとに「選択した項目をCSVでエクスポート」を行うのがコツです。

すべてのCSVがダウンロードされたら、Gem「UbersuggestCSVキーワード・検索ボリューム抽出」で関連キーワードを抽出します。なお、「CSVが読み込めない」といわれた場合は、中身をそのままコピペしてください。
次に再検索キーワードですが「GetKeywords」を利用する方法が、もっとも簡単に取得できるのでおすすめです。再検索キーワードは出現2回以上を取得し、記事構成の原稿に保存しておきましょう。
なお、余計な文字列はAIか、もしくはテキストエディタの正規表現での検索・置き換え機能を利用して削除してください。
最後に、関連・再検索キーワードの重複をGeminiなどに、以下のようなプロンプトで削除させましょう。
末尾の数字は無視して、重複するキーワードを削除。
* 完全一致・スペースの有無が違うだけ・語順が違うだけのキーワードはすべて削除
* 末尾の数字は省略せず出力
* 【関連キーワード】【再検索キーワード】なども省略しない次に、顕在・潜在ニーズをAIに類推させるため、Gem「顕在ニーズ・潜在ニーズの分析」にキーワードを入力してください。顕在・潜在ニーズを記事構成原稿にコピペし、メインキーワードの検索意図について把握しておきましょう。
2.検索上位記事のH2見出しの構造を分析・整理
キーワード調査で読者の検索ニーズを把握したら、次に検索結果で上位を占める競合記事を分析します。検索上位記事は、その時点においてGoogleから内容や網羅性が高く評価されているコンテンツだからです。
検索上位記事のH2見出しを抽出し、どのようなセクションを記事構成で設けるかについて検討しましょう。ただし、検索ニーズに沿っていないと判断した場合、必ずしも検索上位記事のすべてのH2見出しを取り込む必要はありません。
また、抽出作業が終わったらH2見出しの順序についても、抽象的から具体的という流れを基本に整理してください。たとえば、「Aとは?」「Aのメリット」だと前者のほうが抽象度が高く、後者は具体性があると判断できます。
ただし、メインキーワードが「整髪料 ランキング」などであった場合、検索ニーズに沿ってランキングを最初に持ってくるべきです。また、クライアントが最終的に成約してほしい商品・サービスによっても、H2見出しの流れを変える必要があるかもしれません。
検索ニーズやCVRなど目的ごとのH2見出しの流れについては、経験を積みつつ学んでいくのが一番の近道です。
3.H2見出しごとに検索してH3見出しを肉付け
骨子となるH2見出しの構成が固まったら、各テーマをより深く解説するためのH3見出しで肉付けします。上位表示記事だけを参照しながら肉付けするとコピペ記事構成になるため、AIでH2見出しを検索する方法がおすすめです。
たとえば、以下のようなプロンプトを利用すれば、H3見出しとするべき内容を把握しつつ肉付けできます。
H2見出しを入力するので内容を検索して調査し、ポイントをそれぞれH3見出しにし、各H3の下に本文で説明をつけて出力してください。
* 各H3はポイント名のみで構成し、そのなかに説明は含めないでください。説明はその下の本文として書いてください
* まとめは不要です
* 応答・確認テキストは不要です
出力形式の例:
## 入力したH2
### ポイント名
このポイントに関する説明文をここに記載します。検索は人間よりAIのほうが何十倍も速いため、積極的に活用すると素晴らしく効率的に記事構成を進められます。各H2見出しにH3見出しを肉付けし終わったら、以下のようなプロンプトで不要・必要な見出しがないかどうかを確認しましょう。
この記事構成の不要な見出しを指摘してください。また、追加したほうがよい見出しがあれば提案をお願いします。4.見出しで関連・再検索キーワードを回収
作成したH2・H3見出しには、調査段階で洗い出した関連・再検索キーワードを自然な形で組み込んでいきます。見出しにキーワードが適切に配置されていると、読者は自分の知りたい情報がどこにあるかを瞬時に判断できるからです。
また、見出しで関連・再検索キーワードが組み込まれていると、リサーチ・執筆時に自然と内容が定まります。読者の検索ニーズに沿ったコンテンツになるため、検索エンジンから評価される可能性が高くなるのです。
なお、関連・再検索キーワードの回収に関して、キーワードすべてを見出しに入れる必要はありません。
たとえば、本記事の記事構成において「Web記事 構成」は「SEO・Web・レビュー記事によくあるH2見出しのパターン・テンプレート」見出しで回収しています。「Web記事」というキーワードは回収しているものの、見出しには「構成」は入っていません。
つまり、今回の場合は「Web記事」という「関連する箇所以外」の単語を見出しで回収しているだけです。関連・再検索キーワードの回収の仕方については、実際に記事構成を何度も見返してもらうのが理解の早道だと思います。
5.回収できなかった関連・再検索キーワードの見出しを追加
回収しきれていない関連・再検索キーワードのなかに、重要な要素がある場合はH2・H3見出しの追加を検討しましょう。
上位記事になかった見出しになるのであれば、記事の独自性としてGoogleに評価される可能性が高いです。また、多くの記事が見落としたニッチながらも読者が抱くであろう疑問に答える見出しを追加できれば、差別化要因となり得ます。
なお、回収しづらい見出しは「〇〇に関するよくある質問」として、FAQ形式でまとめの前に配置するのが定石です。
6.内容が重複した見出しがないか確認
記事構成を最終チェックし、各見出しが示唆する内容が互いに重複していないかを十分に精査します。なお、人間だけでは重複の発見に見落としが出がちなため、先述した以下のプロンプトを活用してください。
この記事構成の不要な見出しを指摘してください。また、追加したほうがよい見出しがあれば提案をお願いします。よくあるパターンとして、「〇〇のデメリット」「〇〇の注意点」や「〇〇のメリット」「〇〇の特徴」は重複しやすいです。
なお、SEOライターの場合は重複見出しで同じ内容を書いていると、当然ですがクライアントからの評価は下がります。記事構成の段階で徹底的に重複を排除して、スマートかつ魅力的なコンテンツを目指しましょう。
7.記事タイトルを決定
洗練された記事構成が完成したら、検索ニーズに刺さるタイトルを30文字以上40文字以下で検討しましょう。
なお、SEO記事のタイトルではできる限りメインキーワードを最初のほうに持ってくるのが基本です。キーワード=検索ニーズであり、視線は画面左を始点として動くため、最初に持ってくるのがもっとも訴求できる方法となります。
たとえば、「消費者金融 ランキング」という記事構成のタイトルで、よい例と悪い例は以下のとおりです。
◯ 消費者金融ランキング30選!即日借り入れできる方法や審査の流れも解説!
× 【2025年!完全保存版】消費者金融ランキング30選!即日借り入れの方法も解説
小手先の訴求にこだわるより、メイン・関連・再検索キーワードを可能な限りタイトルに含めるほうがCTRは伸びます。
8.想定文字数を算出
最後に完成した記事構成に基づいて、全体の想定文字数を見出し数×300文字で算出すれば完了です。僕の場合は見出し×300文字が平均的ですが、人によっては「275文字」「350文字」などになるかもしれません。
何度か記事を執筆したうえで、文字数÷見出し数を算出して平均的な数値を確定しておくと計算が楽になります。なお、想定文字数を算出するのは「どれくらいの時間で記事が完成するか」を想定するために不可欠です。
僕の場合は記事構成から校正まで約2,500文字/時のスピードなので、1万文字だと4時間で完成する計算です。なお、自分の作業時間を記録していない人は、いますぐに時間管理ツール「Toggl Track」などを導入しましょう。
「記事の想定文字数÷自分の執筆スピード=かかる時間」が算出できれば、スケジュール管理も楽になりますよ。
記事構成を作るときのコツや注意点
記事構成を作るときのコツや注意点は、以下のとおりです。
- キーワード回収の原則
- 記事の目的を明確化
- 検索意図に基づいた関連・再検索キーワード選定
- 競合記事の分析
- 抽象から具体が見出しの流れの基本
- メインキーワードで見出し順を考慮
- シンプルかつ端的な見出し
- H4見出しはできるだけ避けるのを推奨
- 見出しの粒度や表現を統一
- キーワードが多すぎるときの対処法
上記のコツを押さえて構成案を練り上げ、読者の満足度を高めるコンテンツ作りに役立てましょう。
キーワード回収の原則
効果的な記事構成を作成するためには、関連・再検索キーワードを網羅的に回収するのが不可欠です。ユーザーが検索時に用いる言葉や関連する疑問を構成段階で盛り込むと、検索意図への合致度が高まります。
関連・再検索キーワードを回収するには、手間はかかりますがしっかりとした調査を行う必要があります。手間がかかるからと関連・再検索キーワード調査をせずに記事構成をするなら、検索上位表示はあきらめてください。
それこそ、検索上位に表示する可能性のない記事を制作するという、究極の無駄な時間になりますので推奨しません。
記事の目的を明確化
「CVR獲得」「認知度の向上」など記事を作成する目的を明確にしておかなければ、適切な記事構成は作り上げられません。
たとえば、企業イメージや認知度向上のためならば、PVの獲得が記事の目的として設定されます。一方、商品・サービスのCVR獲得が目的の場合、いくら上位表示されてPVが獲得できても成約されなければ意味がありません。
たとえば、CVRが目的の場合、検索ニーズとしては不要であってもクライアント企業の商品・サービス紹介の見出しが必要です。また、商品・サービス紹介へ自然に導くための見出しの流れを考えなければなりません。
「どのような目的で記事が必要なのか」は、ブロガーやライターならつねに意識しておきたいところです。
検索意図に基づいた関連・再検索キーワード選定
1つのメインキーワードに2つの検索意図があり、関連・再検索キーワード選びが大切になるケースが多々あります。
たとえば、「建設業 ホームページ」の場合、「デザインを参考にしたい」「制作の方法を知りたい」という2つのニーズがあります。どちらの検索意図に基づいて記事を執筆するのかを決定し、テーマに沿った関連・再検索キーワードを選定しましょう。
なお、実際に上記のキーワードを検索し、上位コンテンツをジャンル分けすればどちらのテーマにするべきかは明白になります。ギャラリーサイトが「デザインを参考にしたい」というニーズを満たしており、1つの記事で太刀打ちするのは不可能だからです。
したがって、「制作の方法を知りたい」という検索ニーズに合致したコンテンツを作成するのが効果的となります。
競合記事の分析
優れた記事構成を作成するには、検索結果で上位表示されている競合記事の徹底的な分析が欠かせません。上位記事は、多くのユーザーと検索エンジンから「検索意図を満たしている」と評価されている模範解答だからです。
複数の競合記事を比較分析し、共通したトピックを洗い出すと、メインキーワードで解説すべき必須項目が見えてきます。そのうえで独自の切り口や専門的な知見をくわえ、差別化された優位性の高いコンテンツを生み出しましょう。
抽象から具体が見出しの流れの基本
読者にとって理解しやすい見出し構成の基本は、抽象的な概念から具体的な説明へと展開する流れです。人はまず物事の全体像を把握してから、個々の詳細な情報を受け入れるほうが内容をスムーズに理解できます。
たとえば、「ブログのはじめ方」というテーマなら、「ブログとは」といった抽象的な見出しを最初におきます。その後、「ブログをはじめるメリット・デメリット」「ブログをはじめる流れ」など具体的な見出しへと進むのです。
メインキーワードで見出し順を考慮
見出しの順番を決定するときには、ユーザーがもっとも重要視するであろうメインキーワードを軸に考慮すべきです。ユーザーは自身の課題に直結する情報を優先的に求めているため、記事の前半に配置すると離脱を防ぐ効果があります。
たとえば、「SEO対策 具体例」というキーワードなら、最初に具体的な対策例を見せるほうがニーズに応えられます。重要な情報ほど先に提示する原則は、読者のエンゲージメントを高めるうえで非常に効果的です。
見出しの順序については上位記事を参考にしつつ、どうすれば検索ニーズに応えられるかを模索しましょう。
シンプルかつ端的な見出し
わかりやすく可読性の高い記事にするためには、各見出しをできる限りシンプルかつ端的な表現にするのが推奨されます。セクションに何が書かれているかを瞬時に読者へ伝えるのが、見出しの役割だからです。
たとえば、「〇〇を解決するための効果的な方法についての考察」という見出しは、冗長で瞬時に内容を理解できません。しかし、「〇〇を解決する3つの方法」とすれば、読者は一目で要点を把握して目当ての情報があるかどうか判断できます。
H4見出しはできるだけ避けるのを推奨
記事構成を作成するときに、H4以下の深い階層の見出しを多用するのは原則として避けるようにしましょう。見出しの階層が深くなるにつれて記事全体の構造が複雑化し、読者が現在地を把握しにくくなります。
情報が細分化されすぎると、話の全体像が見えづらくなり、かえって読者の理解を妨げてしまいます。H2とH3を基本としたシンプルな構造を維持するように心がけ、読者のわかりやすさを最優先しましょう。
なお、現役のプロSEOライターである僕は、めったにH4見出しを記事構成段階から使いません。H4見出しを避けるためには、H3見出しをH2見出しに変更できないかをまず検討してください。また、本当にH4見出しの内容が必要かどうかについても考えなければなりません。
見出しの粒度や表現を統一
記事構成の完成度を高めるには、各見出しの情報量・粒度・文末の表現スタイルに一貫性を持たせましょう。同じ階層にある見出しの粒度や表現が統一されていると、記事全体のリズムが整い読者のストレスを軽減できます。
文末の表現スタイルは、名詞・動詞のどちらかで終わるのかをそろえると、統一感が出て読みやすくなります。また、H3見出しの情報量と粒度(解像度)についても、統一感があるほうが可読性があがり好ましいです。
粒度・情報量について好ましい例とあまり推奨されない例は、以下のとおりです。
H2 ブログをはじめるメリット
H3 収益を得られる可能性がある
H3 自分の情報を発信できる
H3 スキルアップが可能 × 形容動詞で終わってる
H3 スタートするときに低コストではじめられる × ほかの見出しより長い
H3 Googleアナリティクスが使えるようになる × 粒度が小さい
たとえば、「Googleアナリティクスが使えるようになる」は「マーケティングスキルが学べる」などにするべきです。1つだけ、ほかの見出しと比較して解像度が高すぎ、粒度が小さくなっているからです。
また、「スタートするときに低コストではじめられる」は単純に「低コストではじめられる」とするのが適切でしょう。
キーワードが多すぎるときの対処法
対策したいキーワードが多すぎる場合は、テーマを絞るか複数の記事に分割するアプローチが有効です。1つの記事にあらゆるキーワードを詰め込むと主題が散漫になり、どのユーザーの検索意図にも応えられません。
まずは、調査した関連・再検索キーワードをそれぞれ、検索意図が近いもの同士でグループ分けします。そのうえでもっとも重要な中心テーマに沿ったグループに絞り、関連性が低いキーワード群は別記事として独立させるのが賢明です。
ただし、ビッグキーワードを狙う記事はどうしても関連・再検索キーワードが多くなるのは避けられません。僕の経験上、30個~40個程度のキーワードなら、十分に記事構成の見出しで回収できるはずです。
SEO・Web・レビュー記事によくあるH2見出しのパターン・テンプレート
目的のはっきりしたコンテンツの構成には、読者の検索意図に応じて最適化された普遍的な「型」が存在します。確立された見出しテンプレートを理解して活用すれば、満足度の高い記事構成を効率的に作成できます。
商品・サービスの紹介系の記事構成テンプレートは、以下のとおりです。
H2 ◯◯とは
H2 ◯◯の種類
H2 ◯◯の特徴
H2 ◯◯のメリット・デメリット
H2 ◯◯の口コミ・評判
H2 ◯◯のおすすめサービス◯選
H2 ◯◯をするポイント
H2 ◯◯をするときの注意点
H2 ◯◯を利用する流れ
H2 ◯◯の利用がおすすめの人(もしくは、シーン・状況など)
H2 ◯◯をしたいなら△△もおすすめ!(CVRへ誘導)
H2 ◯◯に関するよくある質問
もちろん、紹介する商品やキーワードによって流れは変わりますが、上記のテンプレートはかなり応用できるはずです。
ChatGPT・Gemini・Claudeで使える記事構成サポートプロンプト
ChatGPT・Gemini・Claudeで使える記事構成サポートプロンプトは、以下のとおりです。
- 顕在・潜在ニーズ分析
- UbersuggestのキーワードをCSVから抽出
- 上位表示記事の見出し構造からH2見出しを抽出
- H3見出しの内容を自動で検索→H3見出しを自動で作成
記事構成の作業を効率化してくれるプロンプトを活用し、よりクオリティの高いコンテンツを目指しましょう。
顕在・潜在ニーズ分析
入力したキーワードに対する顕在ニーズ(検索する際の明確な目的)・潜在ニーズ(検索の背景にある隠れたニーズ)を分析してください。
#ルール
- それぞれ、3つずつあげる
- 箇条書きはそれぞれ1文にする
- 文末に句点を使わない
- 「:」などの記号を使わない
- ユーザーに表示される改行を行う
#出力形式
顕在ニーズ
・◯◯
・◯◯
・◯◯
潜在ニーズ
・◯◯
・◯◯
・◯◯UbersuggestのキーワードをCSVから抽出
CSVファイルから「キーワード」と「検索ボリューム」を抽出し、重複データを削除しながら箇条書きで出力してください。データは必ず省略せずに出力し、「メタ視点」でルールを厳守しているかを確認します。
# 要求事項
- CSVデータから「キーワード」と「検索ボリューム」を抽出する。
- 重複するデータは省き、個別に抜き出して箇条書きにする。
- 抽出したデータの省略は不可。
- 異なるCSVファイルが複数ある場合も考慮し、1つのリストにまとめる。
- 「メタ視点」に立ち、ルールを守れているかを確認。
- 解決方法はシンプルにし、プログラミングは必要最低限にする。
# 手順
1. 読み込んだCSVデータに対し、「キーワード」と「検索ボリューム」の列を抽出する。
2. データをすべて確認し、重複を取り除く。
3. 「キーワード」と「検索ボリューム」を箇条書き形式で出力。
4. 出力プロセスが要求通りであることを念頭におき、メタ視点からのチェックを行う。
# 出力フォーマット
- 箇条書き形式で、「キーワード」とそれに対応する「検索ボリューム」を出力。
- 各行に「キーワード 検索ボリューム」という形式で記述。
# 出力例
- メーカー 売上 ランキング 140
- メーカー 業界研究 110
- メーカー 営業 楽 50
- メーカー ホワイト ランキング 40
- メーカー業界 大手 30
- メーカー 利益率 ランキング 30
- メーカー 売上高 ランキング 20
- メーカー 業界分析 20
- メーカー ランキング 売上 10
# 注意事項
- 複数のCSVがある場合、すべてのデータを統合し、重複を除去する。
- メタレベルで、処理にミスがないか、自身で確認を行うようにしてください。上位表示記事の見出し構造からH2見出しを抽出
「上位表示記事の見出し構造からH2見出しを抽出」プロンプトの使い方は、以下のとおりです。
- AIの入力欄に「メインキーワード:〇〇」と入力
- H2・H3などの見出し階層がわかるように、参照する記事構成をコピペで入力していく
インプットとして上位の記事構成を受け取り、H2見出しを網羅的にリスト化するプロンプトを実行します。
以下の要件に従い、出力内容を形成してください。
- 同義・重複するH2以外は網羅的に出力すること
- 元のH2の意味を守りつつSEO記事の見出しとして表現を整える
- 高い抽象度から具体性の高い順に、ユーザーが理解しやすいよう論理的にH2を並べ替えること
- メインキーワードの顕在ニーズに合致するH2は可能な限り冒頭に配置すること
- H2見出し以外の出力は不要
- メインキーワード可能な限り盛り込んでH2見出しを作成すること
- 日本語として自然な助詞(の、に、による、など)を適切に使用すること
- キーワードが含まれる場合は、できるだけ文頭に配置すること
- 見出し同士の関係性が明確になるよう、類似した表現や助詞を使用すること
- 「〇〇の概要」ではなく「〇〇とは」という表現を使用すること
# ステップ
1. 入力した記事構成からH2のみを抽出する(新規作成は不可)
2. 同義・重複するH2、およびH3として解釈できそうなH2を削除する
3. 抽出したH2を以下の順序で並べ替える:
- メインキーワードの顕在ニーズに合致するH2を冒頭に配置
- 概要的な内容から具体的な内容の順に配置
4. 各H2を、以下の要件でリライトする:
- 元の意味を保持したままSEO記事向けの表現に整える
- メインキーワードは可能な限り文頭に配置
- 見出し同士の関係性が明確になるよう、類似した助詞を使用
5. 作成した記事構成がプロンプトの要件を満たしているか確認:
- すべてのH2が元の記事構成から抽出されているか
- 新規作成したH2が混入していないか
6. 修正が必要な場合はステップ1に戻り、再処理する
# Output Format
- 各H2見出しは以下の形式で出力してください:
```
H2 [変更された見出し]
H2 [別の変更された見出し]
```
# Examples
- Input:
```
H2 正しいダイエット方法
H3 体重を毎日計測する
H3 食べ過ぎ・食べなさすぎに気をつける
H2 健康的な食事
H2 ダイエットの注意点
H2 効果的なエクササイズ
H2 ダイエット
```
- Output:
```
H2 ダイエットとは
H2 注意点と対策
H2 健康食
H2 効果的な運動
```
- Note: 参照例としてアウトプットを示しており、実際の例は内容に応じて異なります
# Notes
- 出力する際、同義・類似な表現を統一しつつ、簡潔で明確な内容にリライトしてくださいH3見出しの内容を自動で検索→H3見出しを自動で作成
「H3見出しの内容を自動で検索→H3見出しを自動で作成」は、2つのプロンプトに分かれており、使い方は以下のとおりです。
- 最初のプロンプトでH3見出しの内容が検索・出力されるので、コピーアイコンでマークダウンでコピー
- 2つ目のプロンプトに入力してH3見出しを生成
H2見出しを入力するので内容を検索して調査し、ポイントをそれぞれH3見出しにし、各H3の下に本文で説明をつけて出力してください。
* 各H3はポイント名のみで構成し、そのなかに説明は含めないでください。説明はその下の本文として書いてください
* まとめは不要です
* 応答・確認テキストは不要です
出力形式の例:
## 入力されたH2見出し
### ポイント名
このポイントに関する説明文をここに記載します。# H3見出し作成タスク
入力テキストの「見出し」と「太字」から、適切なH3見出しを作成してください。
# H3見出し作成の基本ルール
## 入力ソース(最重要)
* 入力テキストの「見出し」または「太字」から抽出
* 上記以外(箇条書き・本文など)からの抽出は禁止
* 新規トピックの追加・創作は禁止
## 見出し形式
* プレーンテキストで出力
* 各行を「H3 」で開始
* 一貫した文末表現(動詞か名詞)を使用
## 見出しの質
* H2見出しのテーマと一致させる
* 重要度順に並べる
* 1つのトピックに焦点を当てる
* 中学生でも理解できる表現を使用
# ステップ
1. **入力を分析**: H2見出しのテーマを確認します。
2. **主要なトピックを特定**: 入力テキストから導出できる重要なトピックを決定します。
- マークダウン記法の見出しや、太字が重要なトピックです。
- 見出し・太字以外でのトピック作成は禁止です。
3. **H3見出しを作成**:
- H2テーマと一致するH3見出しを策定します。
- 各見出しの内容は重複しないようにしてください。
- 文末の一貫性を保つ(動詞または名詞を使用)。
4. **重要度順に整理**: H2見出しの下で全体のトピックへの重要度に基づいてH3見出しを並べ替えます。
5. **わかりやすさ・言語的な自然さのための洗練**: H3見出しを自然でわかりやすいかどうか確認し、洗練させてください
6. **メタ視点で再確認**:メタ視点でプロンプトが遵守されているかどうか再確認し、守られていないならステップ1.に戻ってください
# 入力例
## プライバシー保護
(本文)
## ブランディング効果
(本文)
# 出力例(プレーンテキスト)
H3 プライバシー保護
H3 ブランディング効果
(例は例示的なものであり、実際のシナリオでは入力で提供された複雑さとコンテンツの深さが一致することを確認してください)読者の検索ニーズを十分に反映した記事構成を作ろう!
SEO記事で上位表示を目指すには、設計図となるクオリティの高い記事構成を作成するのが極めて重要です。読者の理解を助けて読みやすさを向上させ、検索エンジンからの評価を高めるだけでなく、執筆の効率を劇的に改善するからです。
関連・再検索キーワードを徹底的に調査し、読者が抱える本質的な悩みを深く理解するのが高品質な記事構成の第一歩となります。次に、検索上位の記事を分析して評価されている要素を把握し、自身の記事に盛り込むべきH2見出しの骨子を固めていきましょう。
さらに、各H2見出しの内容を深掘りしてH3見出しで肉付けし、調査したキーワードを自然な形で回収しながら網羅性を高めます。
一連のプロセスで生成AIや各種ツールを活用すれば、作業時間を大幅に短縮しながら質の高い記事構成を練り上げられます。解説した具体的な手順とコツを参考に、読者の検索ニーズを的確に捉えた質の高い記事構成を作成し、検索上位を目指しましょう。